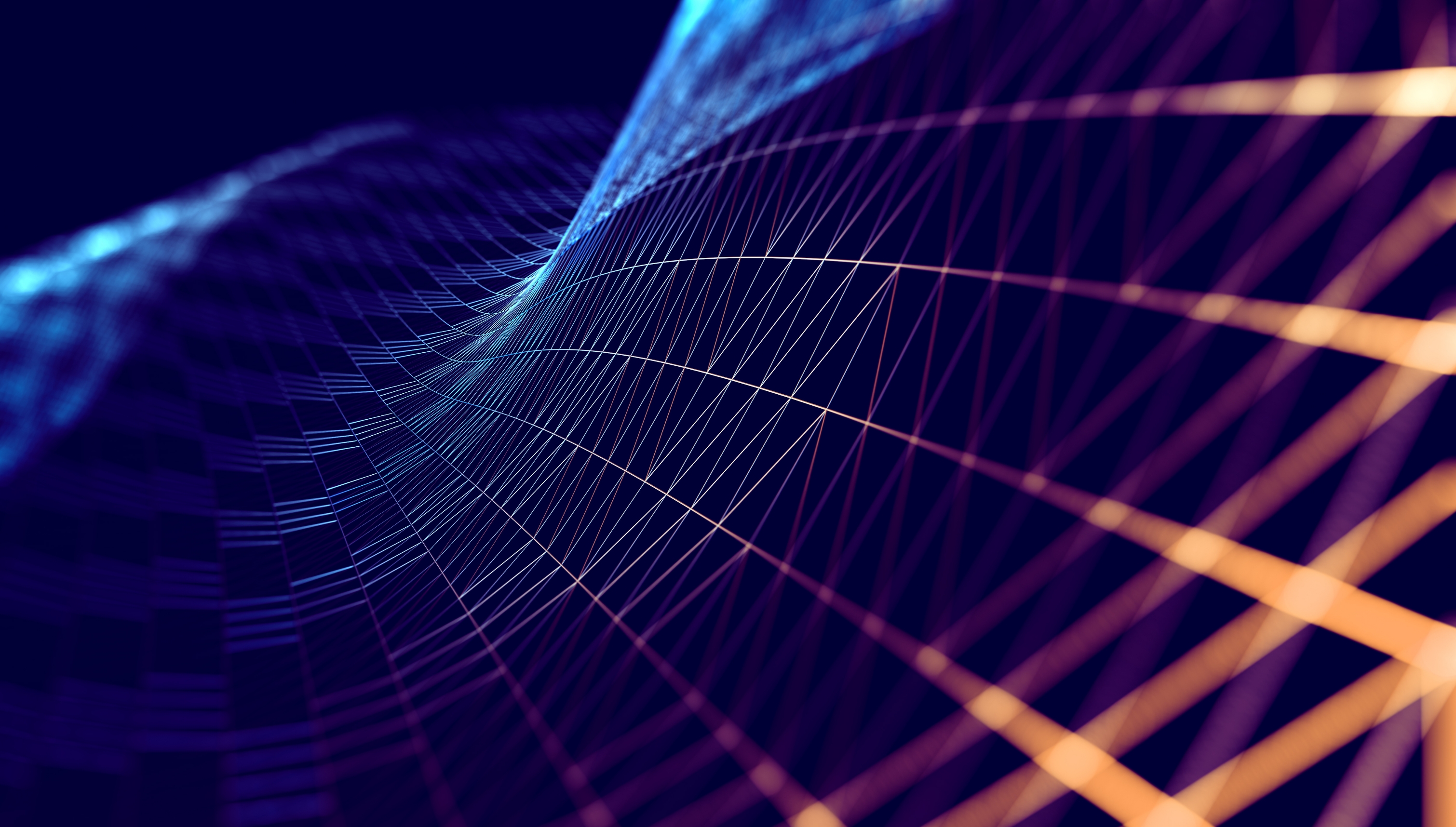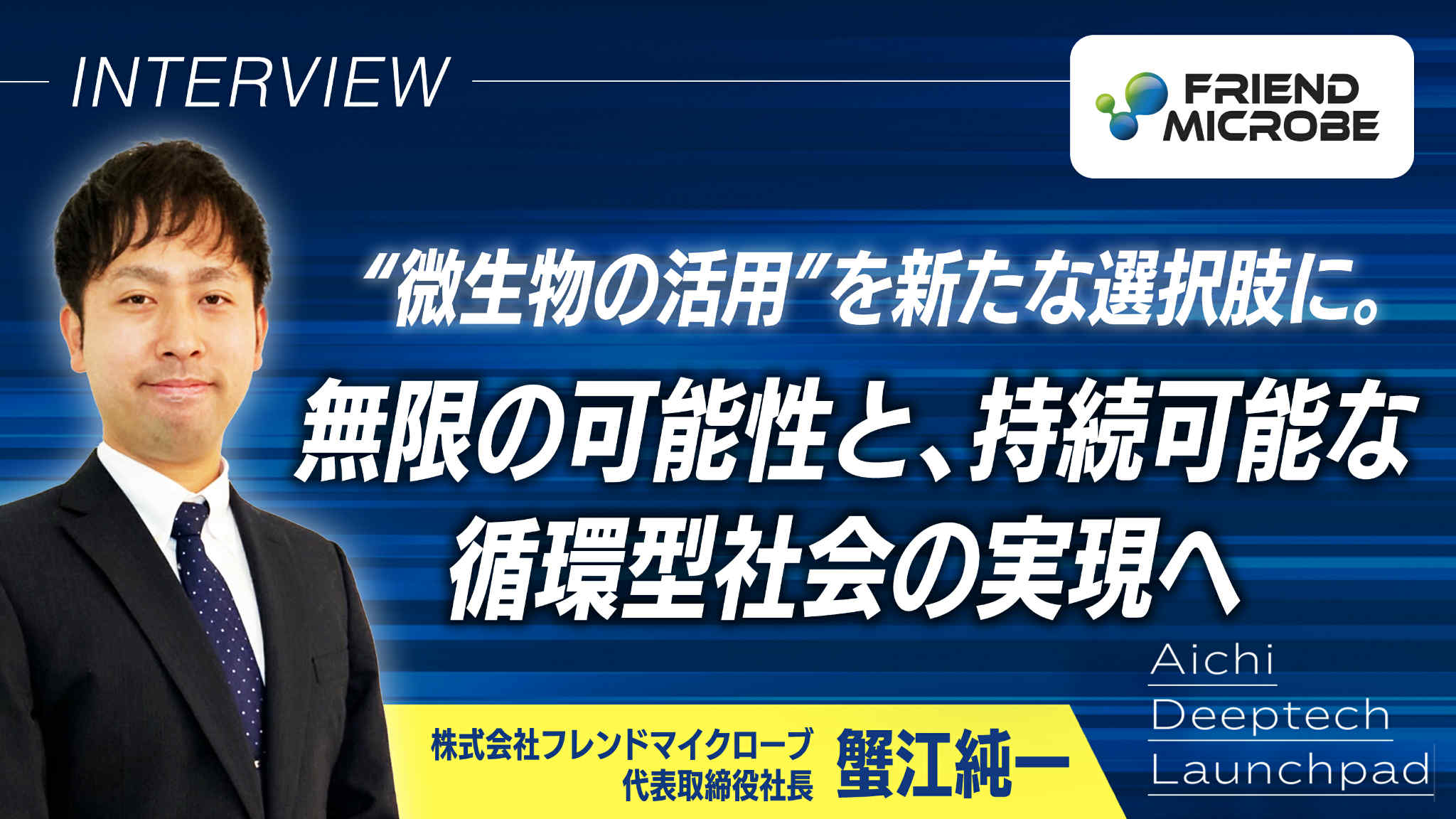2025年7月25日(金)、「Aichi Deeptech Launchpad Acceleration 2025」の採択者を囲んでのキックオフMeet up イベントを名古屋市・STATION Ai(名古屋市昭和区鶴舞1丁目2−32)にて開催しました。本イベントでは、採択者によるピッチ、意気込みスピーチや過去にAichi Deeptech Launchpadに採択されたスタートアップとメンターによる振り返りセッションなど、愛知県のDeeptechコミュニティの機運醸成に向けてさまざまなコンテンツを実施。計60名以上の方にご参加いただきました。
【Aichi Deeptech Launchpad Accelerationとは】
Aichi Deeptech Launchpad Accelerationは、愛知県の産業構造と親和性の高い分野のディープテック系スタートアップを中心にハンズオン支援を行い、その技術の社会実装や破壊的イノベーションによる既存市場の転換、社会課題の解決、新規市場の創出を図ることを目的としたディープテック特化型のアクセラレーションプログラムです。

開会のご挨拶
開会の挨拶では、愛知県経済産業局顧問・柴山政明氏より「愛知県では、2018年より全国に先駆け、ものづくり融合型の愛知県独自のスタートアップエコシステムの形成に産学官金で取り組んでいます。その中でも、愛知県庁と名古屋大学を中心に連携をはかりながら、ディープテック分野の応援により注力しております。年々ディープテック系の企業が成長をしてきている中で、Aichi Deeptech Launchpad3年目として、今日集まっていただいた方々と共にさらにコミュニティを拡大していきたいです。」とコメントをいただきました。
また、新たな取り組みとして全国の他地域との連携を強化し、さらなるイノベーションを生むため、昨年の12月に東京都とMOUを結んだことを報告。東京都副知事・宮坂学氏を呼び込み、会場は盛り上がりを見せました。
宮坂氏からは「“シリコンバレーのエコシステム”とはいいますが、 “アメリカのエコシステム”とは言わないように、スタートアップエコシステムというのは都市単位での役割が非常に重要になると考えています。名古屋市というものづくりやディープテックに非常に強い都市と、東京という違った個性を持つ都市同士が連携して、エコシステムを連結していくことはとても意味があることだと思います。そこからさらなる他の都市との橋渡しは我々が責任を持って行いますので、ともに世界に羽ばたいていきましょう。」と、来場者にエールを送りました。
2025年度 採択スタートアップのご紹介
「採択者によるピッチ&意気込み」セッションでは、以下3名のコメンテータをお迎えし、今年度のAichi Deeptech Launchpadに採択されたスタートアップ5社が自社のピッチやプログラム期間中で取り組みたいことなど意気込みを発表しました。
<コメンテータ>
内田・鮫島法律事務所 奈良大地氏
STATION Ai 中島順也氏
UntroD Capital Japan 平泉裕美氏
株式会社IZANA/大前 緩奈氏によるピッチ

<事業内容>
株式会社IZANAは、超高感度磁気センサを開発・製造・販売をする名古屋大学発スタートアップとして、今までに無い磁気センサのソリューションを提供しています。「磁気センサ」というものはスマートフォンにも必ず入っている身近な電子部品で、それを15,000倍の高精度で制作したものが超高感度磁気センサです。主に製造業の事業会社さまに向け、超高感度磁気センシングの活用に向けたPoCから量産支援までトータルで提供しています。
我々は、製造業における品質管理の重要性に注目しています。製造業の現場において、事業者さまが抱える事業リスクのひとつに「異物混入」があります。異物混入が起きてしまう結果、販売停止や商品回収という課題が発生するという状況があります。こういった異物混入に起因する課題に対して、「超高感度磁気センサ」を活用することで異物を検知・省くことで、より高い水準の品質保証を実現したいと考えています。
現在の取り組みの一つとして、リサイクル分野で超高感度磁気センサを使用し、従来困難であった異物を検知した事例も出てきています。シンプルではありますが、高い磁場感度はもちろん、従来は困難であった磁気ノイズの大きい工場環境下での超高感度磁気センサ活用を可能にするなど、弊社でしか提供できない解決策であると考えています。
<目指すゴール>
パートナー企業さまと共に販売可能なシステムを作成していき、超高感度磁気センサによる微小磁気異物検知システムの製品版の作製を目指します。具体的には、要素技術を統合・最適化しプロトタイプによる実証実験を行い、製品版のシステムを完成させたいと考えています。現在はまだ資金調達を行なっていないので、事業化戦略・知財戦略等における助言をいただきながら、将来につなげていきたいです。
<コメンテーターより>
「大学発・センサーの技術」と聞くと、ニーズをどれだけ捉えているかが気になるという方もいらっしゃるかと思います。その点について、私自身が大学で学んだ磁気に関する知見をふまえて強く感じているのは、「超高感度磁気センサ」は非常に応用先がある技術だということです。製品化にあたっては、応用先ごとに異なる仕様や特徴を持った製品が出来ると思います。ぜひ今後の開発において、応用先のニーズを明確にし、それに最適化した製品の方向性を整理しながら、進めていただければと思います。
株式会社Helical Fusion/田口 昂哉氏によるピッチ

<事業内容>
Helical Fusionは、核融合エネルギー(フュージョンエネルギー)の実用化を目指すスタートアップです。太陽の中では、「核融合」と呼ばれる反応により、膨大なエネルギーが生み出されています。ただ、地球は太陽と距離がとても離れているので、そのエネルギーのうちわずかしか届いていないのです。核融合反応を地球上で人工的に再現して、直接エネルギー源として利用していく仕組みを作ろうとしています。
私たちは、“日本にもうひとつ太陽をつくろう。”をスローガンに、「Helix Program」という計画のもと、2030年代に世界初の「実用発電」の達成を目指しています。核融合は、海水から豊富に採取できる燃料を用いることからも、地下資源に乏しい日本の「エネルギー自給率の低さ」という課題に対して、技術でエネルギーを生み出すという、抜本的な解決策となります。現在エネルギー自給率が15%程度とされる日本の状況から、「エネルギー輸出国:日本」という未来にもなれる可能性をも持っていると考えています。
現状、電源として実用に足る核融合プラントを開発している企業は世界でもほとんど存在しない中、Helical Fusionは「定常運転・正味発電・保守性」という商用炉の三要件にこだわって開発を進めています。そして、これまで日本で60年以上、国家プロジェクトとして蓄積されてきた科学技術の基盤をもとに、いよいよ「ものづくり」のフェーズに入っています。日本の企業さまとのパートナリングを力に、最短ルートでフュージョンエネルギー実用化を進めます。
<目指すゴール>
世界最先端の工作機械を活用して高精度な重要部品を独自開発するなど、実際に愛知県の企業さまとの協業がスタートしています。日本の中でも高い技術力を持っている愛知県、中部地方の産業の担い手の皆さまと、Helical Fusionの技術を融合することで、日本がエネルギー大国になる未来を本気で目指していきたいと考えています。弊社はADLに3年連続で応募、採択いただいております。それほど素晴らしいプログラムだと感じておりますので、引き続きよろしくお願いします。
<コメンテーターより>
「ものづくりのフェーズに入った」という言葉がとても印象的でした。市場規模としても自動車産業に匹敵する、または超えていく事業規模へと成長する可能性を強く感じています。愛知県が、自動車産業に続き、核融合という新たなエネルギー発電分野においても産業集積地として発展していく未来に期待しています。
株式会社INOMER/桂 典史氏によるピッチ

<事業内容>
我々は、運動機能が低下している方をサポートする「着るロボット」を開発する奈良県のスタートアップです。誰もが日常的にロボットを着て、意のままに動き、自分らしく豊かに生きる世界をビジョンとしています。スニーカーを履くように、どんな方でも気軽にロボットを身につけられる世界を目指しています。
全世界には、脳卒中による片麻痺患者は5,000万人〜8,000万人いるとされており、突然の身体機能の低下は本人だけでなく家族、医療従事者や国にも大きな負担を与える深刻な社会課題です。
我々が開発する着るロボット「inoGear HE-1」は、理学療法士の “技”をもとに設計された歩行リハビリ支援デバイスです。リハビリの中で理学療法士が行う歩行リハビリの属人的な部分(アシストや力の入れ方)をロボット技術によりDX化することで、介助の再現性が出せ、力の差にかかわらず一定の介助が出来るという点が特長です。効率的なリハビリを提供できるだけではなく、このような先端的なツールを導入しているということで、小規模施設にとって集客面での差別化ポイントにもなります。1台あたり40万円程度の価格で、年間1~3人集客できることで採算がとれるという点も訴求していきたいと思っております。
<目指すゴール>
現在、愛知県の国立長寿医療研究センターリハビリテーション科部 加賀谷斉先生と連携し、臨床試験も進めています。プロトタイプとしては完成に近いのですが、プログラム参加中によりユーザビリティの改良を重ねながら、サンプル出荷40台を達成したいと考えています。プロダクトを完成させ、プロダクトマーケットフィットを達成していきたいです。市場に関しては、日本だけでは規模が限られてしまうため、海外展開を早めに準備していきたいと考えています。
<コメンテーターより>
祖母が100歳なのですが、95歳を過ぎたころから歩けなくなり、現在は毎週訪問介護に来てもらっています。そのため、今回の技術は非常に身近な課題として素晴らしい技術だと感じました。実際に35施設で導入しているということで、患者さんやご家族がどの程度改善されたかという具体的な事例をもっとお聞きしたいと思いました。また、導入するリハビリテーション施設・医療機関に対して、今後どうPRしてトラクションを獲得していくのかという戦略についても、ぜひ早めに設計されると良いかと思います。
株式会社Craftide/大石 俊輔氏によるピッチ

<事業内容>
農業の課題として、化学農薬・化学肥料による環境への負荷というものがあります。その対策として政府も「緑の食料システム戦略」というものを定めており、2050年までに化学農薬を50%減、化学肥料を30%減という目標を掲げています。
しかし同時に、環境規制により生産量が落ち、農家さんが困窮してしまうという課題を抱えています。そこで、環境への優しさと生産性向上を両立するために弊社が注目したのが「ペプチド」です。ペプチドは分解されると最終的にアミノ酸になるので環境に負荷がかからず、ペプチドを人工的に使えば、植物を上手に育てることが可能になります。
なぜ、この素晴らしい技術がこれまで使われてこなかったのかというと、「植物の成長にペプチドが作用している」と分かったのが、30年ほど前と、最近の発見だからです。名古屋大学が世界に先駆けていましたが、遺伝子組み換えを使っていることから農業には応用が出来ずにいました。今後は愛知県の強みであるハウス栽培と組み合わせて新しい技術を生み出していきたいです。
<目指すゴール>
環境に優しく、かつ農業の生産性を向上させる新しいソリューションを提供することで、生産者さんにとっては環境にやさしい栽培が出来、消費者にとっては安全で美味しい農作物を購入することが可能になります。プログラム期間中には、より現場に即した具体的なニーズや課題を掘り起こしながら、共同研究型のビジネスモデルとしてマネタイズを目指します。
<コメンテーターより>
消費者の需要性が高い農業分野において化学肥料を減らすというアプローチは非常に有意義であり、素晴らしい技術だと感じます。研究時間が浅いというところもオポチュニティが高く、かつ名古屋大学発という強みもありますので、ぜひ次回は研究開発費支給ありの採択を目指していただきたいと思います。環境に優しいという点はもちろんのこと、「ペプチドを使用した方がより美味しい」などの付加価値を提示できれば、新たな市場開拓にも繋がり、投資家からの評価も高まると思いますので、ぜひそういった点も検証を進めていただければと思います。
FiberCraze株式会社/長曽我部 竣也氏のピッチ

<事業内容>
弊社は4年ほど前に設立した岐阜大学発ベンチャーです。私たちは当たり前のように衣服を身につけていますが、そこにはとても多くの水とエネルギーが使用されています。繊維産業は、石油産業の次に地球環境を汚している産業であると言われています。
その中でも我々は特に大きな問題として「染色」という部分に着目しております。染色のプロセスには、「高温・高圧」処理が必要だからです。
愛知県、岐阜県には染色会社が多く、1950年代から自動機械式の染色装置が広まりました。ファストファッションの台頭で、より安価な染色加工を求めて海外生産へ移行していますが、環境悪化はさらに深刻になっています。一方でヨーロッパでは「CO2・薬品・水を使用しすぎない」というルールが定められており、従来の染色加工には抜本的な変化が必要です。
この課題をひっくり返すには、材料側から変える必要があると考えました。そこで、岐阜大学で30年ほど研究された技術を活用し、新しい材料で解決します。弊社の新素材Craze-tex®は、ポリエステルといった材料に後加工で「ナノレベルのあな」を開けることで、低い温度・圧力で染めることが出来るというものです。
実際に工場で行ったPoCでは、環境へのインパクトとして、最大でC02排出量を75%、水消費量を80%削減するポテンシャルがあります。
その他にも、防虫、UVカット、消臭などの付加価値をつけることも可能であるため、デング熱・マラリアといった世界の社会課題に対しても解決できると考えています。マレーシアの感染症研究機関「マラヤ大学 TIDREC」とはMoA契約を締結し、防虫成分を閉じ込めた高機能性素材の開発の実証実験を本格化しています。
<目指すゴール>
2027年の量産に向けて、現在は素材の研究開発ならびに品質管理の徹底を行なっています。お客さまの要望に応じたサンプル提供に応えるべく、自社のラボ試作装置を作ることを直近の目的としています。かつ、量産後の販売先顧客を50社以上獲得します。我々の先端技術と、私の地元の愛知県一宮市や、岐阜を中心とした繊維産地の高いものづくり技術を組み合わせ、”世界が誇る素材を創る”ことに尽力していまいります。
<コメンテーターより>
ファッション業界においては、ブランドが持つ機能性・メッセージ性が、購入者のニーズを喚起していると感じています。そのような状況の中で、御社がどのようにこの素材をPRし、それをビジネスモデルへどのように反映していくのかに注目して聞いておりました。今後、どのような発信を通じてブランド価値を高めていくのか、その展開を楽しみにしております。
さいごに

<愛知県 経済産業局 革新事業創造部 スタートアップ推進課 戦略推進グループより>
キックオフイベントでは、スタートアップの皆さんの熱量と、それに対する関係者の高い期待を強く感じました。
ディープテックは社会課題に向き合い、可能性を切り拓く分野です。社会実装に時間がかかるからこそ、愛知県としても腰を据えて支援していく姿勢が重要だと考えています。こうした挑戦が愛知県の産業にも新たな刺激を与えることを期待し、地域企業との連携を通じて次の成長につながる取り組みを進めていきます。
今後もこのディープテックコミュニティを育て、挑戦が連続的に生まれる環境を整えていきます。